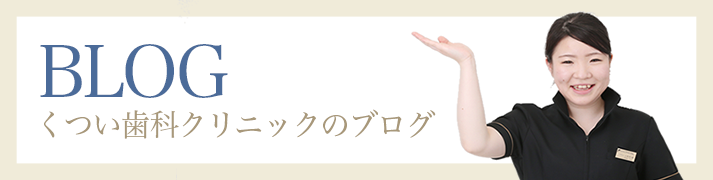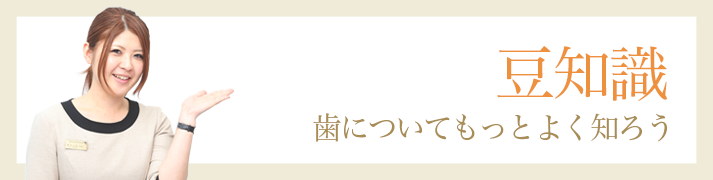オーラルライフレイル予防
揖斐郡池田町の歯医者
くつい歯科クリニックの歯の豆知識
オーラルライフレイル予防についてお話しします。
オーラルライフレイルとはお口の老化のことで、歯の欠損や嚥下機能が低下した状態をいい、将来、寝たきりにつながる要因のひとつです。
皆さんは、どんなシニアライフを送りたいですか?
好きなものを食べたい、健康で若々しい自分でいたい、旅行や外食をたのしみたいなど、理想のシニアライフは
「いい歯」に支えられています。
お口は身体の入り口、命の入り口といわれてるように、歯は日々の生活を支えています。歯には噛む、食べる機能以外にもさまざまな働きがあります。
・表情や顔を整える
・はっきり話す、発音を助ける
・噛む、味わう、食事を楽しむ
・バランスを保ち、力を発揮する
などです。まだまだ先のことと思うかもしれませんが、将来のために、しっかりデンタルケアをしましょう!
・歯科の定期検診を受ける
・万一、歯を喪失しても放置は禁物!
元気なシニアの秘訣はお口にあります。手遅れになる前に定期的な歯の検診をおすすめします。